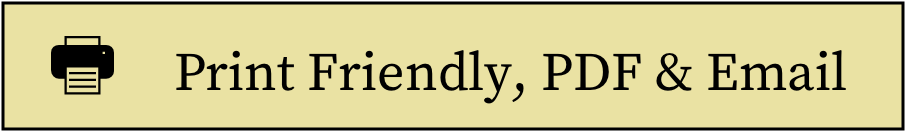- Kazuo YAGI, Applause space, 1974, black-fired earthenware, 22.0 x 16.5 x 14.0cm, Gift of members of the Sodeisha Group 1981, Newcastle Art Gallery collection
- Satoru HOSHINO, God and his medium, not dated, hand-built form, glazed white clay, 28.0 x 23.0 x 56.0cm, Gift of members of the Sodeisha Group 1981, Newcastle Art Gallery collection
1979年、ニューカッスル・アート・ギャラリーで「走泥社:日本の前衛陶芸」と題された展覧会が行われた。これは、オーストラリアではじめて、日本の陶芸家グループ、走泥社の革新的な仕事を取り上げた展覧会で、創立メンバーの八木一夫(1918-1979)、鈴木治(1926-2001)、山田光(1924-2001)を含む32名のメンバーの作品が展示され、オーストラリア各地の主要なギャラリーを巡回した。そうして展覧会が幕を閉じると、走泥社のメンバーは、出品作62点のうち、58点をニューカッスル・アート・ギャラリーに寄贈することに決めた。
同ギャラリーでは、2019年に「走泥社:オーストラリアとのつながり」展の開催を予定している。この展覧会では、走泥社が戦後日本の陶芸界の発展におよぼした影響を再考、再評価し、さらには彼らの仕事と、日本とオーストラリアの現代作家への影響を考察する。
第二次世界大戦が終戦を迎え日本が海外へ広く門戸を開くと、芸術家たちはそれまで知らなかった西洋の芸術運動の吸収に努めた。陶芸界においては1940年代後半に走泥社が創立されたことが特に重要な意味を持った。彼らは一丸となって、数百年の伝統を持ち中国と韓国からの影響を多方面に受けてきた陶芸界の因習に果敢に立ち向かった。グループの名称は、宋磁の鈞窯に特有の「蚯蚓走泥紋」柄に由来している。
1940年代は、走泥社の陶芸家にとって、モダニズムやシュルレアリスムといった海外芸術界の動向を吸収する探索と実験の時代であった。マックス・エルンスト(1891-1976)、パウル・クレー(1879-1940)、ジョアン・ミロ(1893-1983)らの作品に加え、ピカソ(1881-1973)の陶芸作品、さらにはイサム・ノグチ(1904-1988)や辻晉堂(1910-1981)ら日本人彫刻家の作品もまた彼らの心をとらえた。だが、走泥社のメンバーは機能性や伝統的な造形に背を向けたわけではない。特に終戦直後は、多くのメンバーにとって実用品の制作が収入源にもなった。興味深いことに、初期メンバーの大半は代々作陶を続けてきた家の出で、抽象形態による実験的な創作だけではなく、実用品の制作も継続して行い、「人工的に両極化された工芸と芸術とを結びうる、あらゆる活動に邁進するという彼らの流儀」(コート、ウィンテル・タマキ 2003, p.156)を実践した。だが、彼ら自身は伝統的な造形を尊重する立場にあったにも関わらず、活動初期は、新時代の異端者で伝統の破壊を目論む悪者集団だという批判も受けた。
走泥社は、急速な変化を遂げる世界の中で、西洋文化の吸収を通じ、自らの位置づけを根本から見直そうとした。伝統を基盤とする工芸の価値観に徹底的に立ち向かうことを目指したこのグループが、きわめて保守的な古都京都の町で産声を上げたことは驚きではないだろうか。
走泥社が初期に制作した器の多くは、西洋美術からの影響が強い抽象的な装飾を取り込んだ、折衷主義的な比較的シンプルなロクロによる作品であった。八木は1950年にニューヨーク近代美術館で自作が展示された折に「新しいものと古典との結婚、これが私のねらいです。ピカソやクレーの近代絵画と、渋い日本のロクロの味を、作品の上でどう調和させるかが私の仕事です」と語っている(内山 1981)。八木によるロクロの再評価は、ロクロに対する一切の既存の理想論を打ち消し、ロクロを単純に作陶の道具に還元させた。この意識改革が「ザムザ氏の散歩」(1954)の制作へとつながった。この作品のタイトルは、ある朝主人公が目覚めると虫に変身していたというあらすじの、フランツ・カフカ(1883-1924)の小説『変身』に言及している。「ザムザ氏の散歩」は八木自身の作品の変化と、ロクロと決別し、のちに「オブジェ焼き」の名で知られるようになる、より彫刻的で抽象的な創作への転向を示す記念碑的な作品となった。
「走泥社:オーストラリアとのつながり」展に並ぶ走泥社の作品は、多くの点で40年前と同じ新鮮さと現代性を放つ。1998年、走泥社は50年にわたる活動に幕を閉じたが、日本の陶芸界に変革を起こすという使命は大々的に果たされた。日本のみならず世界の陶芸界の発展への彼らの貢献の大きさには議論の余地がなく、その先駆的な作品は、のちの世代の作家の創造性を刺激し、彼らが陶芸の限界を押し広げるための枠組みを提供した。そのことは、走泥社の作品と共に陳列される、日本とオーストラリア両国の現代作家10名の作品からも明らかである。特に陶芸の世界では、過去の造形表現と伝統の分析と再解釈、さらには作家の国外移住や国際交流を通じ、相互の影響を深め合うことで、継続した活性化が図られてきた。実用に縛られない彫刻的な陶芸はもはや目新しいものではなくなった。事実、今という時代においては、多くの作家が彫刻表現としての土の可能性を再発見しているのである。
参考資料
Cort, Louise Allison and Winther-Tamaki, Bert. Isamu Noguchi: a close embrace of the earth. Published by the Arthur M.Sackler Gallery in association with University of California Press, Berkeley, Los Angeles and London. 2003. P.156
Uchiyama Takeo. The Ceramic Artist Kazuo Yagi. From the catalogue to the exhibition, Kazuo Yagi, 1981. National Museum of Modern Art, Kyoto.
筆者
 ケヴィン・ホワイト。イギリスと日本で教育を受け、国際的にその名を知られる陶芸家。現在は、日本の磁器の伝統と19世紀イギリス陶器に見られるジャポニズムの解釈を研究している。1978年に旧文部省による大学院研究支援制度のもと、京都市立芸術大学の故近藤豊教授から陶芸を学ぶ。その後現代陶芸のグループ「走泥社」の元メンバー、佐藤敏のもとで働く。1985年、ロンドンのロイヤル・カレッジ・オブ・アートにて修士課程を修了。現在は、RMIT大学芸術学部に非常勤講師として勤務する傍ら、ビクトリア州エルサムのアーティストコミュニティ、モンサルバットの工房で制作に励んでいる。
ケヴィン・ホワイト。イギリスと日本で教育を受け、国際的にその名を知られる陶芸家。現在は、日本の磁器の伝統と19世紀イギリス陶器に見られるジャポニズムの解釈を研究している。1978年に旧文部省による大学院研究支援制度のもと、京都市立芸術大学の故近藤豊教授から陶芸を学ぶ。その後現代陶芸のグループ「走泥社」の元メンバー、佐藤敏のもとで働く。1985年、ロンドンのロイヤル・カレッジ・オブ・アートにて修士課程を修了。現在は、RMIT大学芸術学部に非常勤講師として勤務する傍ら、ビクトリア州エルサムのアーティストコミュニティ、モンサルバットの工房で制作に励んでいる。